カルノーサイクル
カルノーサイクル
熱と仕事
水を入れた鍋(なべ)に蓋(ふた)をして火にかけると、沸騰して蓋(ふた)がカタカタと音を立てる。
蒸気の圧力が蓋を動かすからである。
つまり、熱が機械的な仕事に変わったのだ。
もっと効率よく熱を機械的な作業に変換できれば、人力ではできない作業も火を利用して行うことができる。
このような発想から、蒸気機関が発明され、改良されていった。
シリンダ内の気体(水蒸気等)を熱で膨張させ、ピストンを押し出せば外部に対し仕事をしたことになる。
ピストンを押し出し切ってしまえば、できる仕事はそれで終わってしまう。
ところが、何らかの方法でピストンを元の位置にもどせれば、反復して仕事を継続することができる。
ピストンをカムにつないで車輪を回転させれば、車輪の慣性モーメント(回転を続けようとする勢い)でピストンは元の位置に戻ることが可能だ。
これがエンジンの基本原理である。
カルノーサイクルとは
ピストンを押し出せるときに内部の気体は膨張し、ピストンが元の位置に戻るときに圧縮される。
膨張と圧縮を交互に繰り返すことをサイクルという。
サイクルとは、熱を仕事に変えるための手段なのだ。
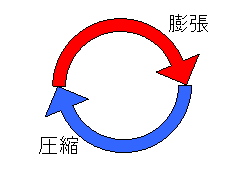
ここで膨張の仕方を二通り考えよう。
「熱の出入りを許す膨張」と「熱を出入りさせない膨張」だ。
「熱を出入りさせない膨張」を断熱膨張という。
断熱膨張は、シリンダを厳重に断熱材で包み込んだ状態で気体を膨張させるイメージだ。
ここで、ボイル=シャルルの法則を思い出そう。
熱の出入りがない状態で気体が膨張すると、温度は下がるのだ。
つまり、断熱膨張は内部の熱は一定だが温度が下がる膨張なのである。
これに対し、「熱の出入りを許す膨張」を等温膨張という。
等温膨張は、薄い金属製のシリンダで気体を膨張させるイメージだ。
気体が膨張すると温度は下がるのだが、熱が楽に流入するので気体の温度は一定に保たれる。
等温膨張は、温度は一定だが、内部の熱は増加する膨張なのである。
圧縮についても同様に「断熱圧縮」と「等温圧縮」の二通りを考えることができる。
断熱圧縮では温度が上がるが、等温圧縮では熱を吐き出すので温度は一定だ。
さて、さきほどのサイクルにおいて、膨張の前半を等温膨張、後半を断熱膨張としてみよう。
さらに、圧縮の前半を等温圧縮、後半を断熱圧縮とする。
この4工程からなるサイクルがカルノーサイクルだ。
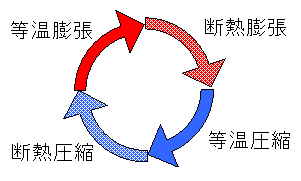
カルノーサイクルが一巡するときに、等温膨張の工程で熱がシリンダに入り、等温圧縮の工程で熱がシリンダから吐き出される。
熱を与えて仕事をさせる仕組みを熱機関というが、熱を与えるとは、等温膨張させることなのだ。
カルーサイクルには、必ず等温圧縮の工程がある。
等温圧縮では熱が吐き出されるのだ。
吐き出される熱は、元々等温膨張時に入って来た熱の一部である。
言い換えれば、入ってきた熱を100%仕事に変えることはできないのである。
カルノー機関
カルノーサイクルでは、熱の一部を仕事に変え、さらに同じ動作を反復することができる。
つまり、カルノーサイクルは熱機関として利用できるのだ。
カルノーサイクルを利用した熱機関をカルノー機関という。
(ただし、カルノー機関は、理論的に成り立つのであって、現実的ではない)
カルノー機関では、流入した熱の一部を捨てるものの、それ以外の熱は外部に対する仕事になる。
等温膨張工程で流入した熱QHと、等温圧縮工程で捨てた熱QLの差が仕事Wなのだ。
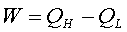
与えた熱(等温膨張工程で流入した熱)に対して、どれほど仕事したかの比率をカルノー効率といいη(エータ、ギリシャ文字)という。
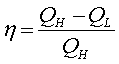
これを見ると、カルノー効率は熱源の温度のみに依存することが分かる。
作業物質(シリンダ内部の気体)や、サイクルを回転させるスピードには無関係なのだ。
■次のテーマ:熱の仕事当量
スポンサーリンク
2007/12/03